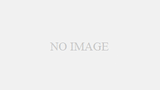言はずして後に於て事発れなば、亦、族滅を免れじ。
奈何せん。又聞く、関内淪没し、(二六)李孝常、華陰を以て叛けりと。
上、其二弟を囚へ、之を殺さんと欲す。
我が輩の家屬は皆西に在り。能く此慮無からんやと。』
二人に皆懼れて曰はく、然らば則ち計将に安くに出でんとする」と。
徳戡曰はく、『驍果若し亡げなば、之を俱に去らんに若かじ』と。
二人皆曰はく、『善し』と。
因つて轉た相招引す。内史舎人元敏・虎牙郎将趙行樞・鷹揚郎将孟秉・(二七)符璽郎牛方裕・直長許弘仁・薛世良・城門郎唐奉義・醫正張愷・勲侍楊士覧等、皆之と謀を同じくし、日夜相結約し、廣坐に於て明らかに叛計を論じ、畏避する所無し。
宮人あり蕭后に白して曰はく、『外間、人人、反せんと欲す』と。
后曰はく、『汝が之を奏するに任す』と。
宮人、帝に言ふ。帝大いに怒り以為へらく言ふべき所に非ずと。
之を斬る。其後、宮人復た后に白す。
后曰はく、『天下の事、一朝にして此に至る。救ふ可き者無し。何ぞ之を言ふを用ひん。徒に帝をして憂へしめんのみ』と。
是より。復た言ふ者無し。
趙行樞、将作少監宇文智及と素より厚し。楊士覧は智及の甥なり。
二人、謀を以て智及に告ぐ。
智及大いに喜ぶ。
徳戡等、三月望日を以て黨を結びて西に遁れんことを期す。
智及曰はく、『主上、無道なり雖も、威令尚ほ行はる。卿等亡げ去らば、正に竇賢の如く死を取らんのみ。今、天、實に隋を喪し、英雄竝び起り、心を同じくして叛く者、已に數萬人なり。因って大事を行はば、此れ帝王の業なり』と。
徳戡等、之を然りとす。
行樞・薛世良・智及の兄右屯衛将軍許公化及を以て主と為さんと請ふ。
結約既に定まり、乃ち化及に告ぐ。化及、性駑怯にして、之を聞き、色を變じ汗を流す。
既にして之に従ふ。
徳戡、許弘仁、張愷をして、(二十八)備身府に入り、識る所の者に告げて云はしむ、『陛下、驍果が叛かんと欲するを聞き、多く毒酒を醞し、享會に因りて盡く之を鴆殺し・獨り南人と興に此に留まらんと欲す』と。
驍果皆懼れ、轉た相告語し、反謀益々急なり。
乙卯、徳戡悉く驍果の軍吏を召し、諭すに為す所を以てす。
皆曰はく、『唯だ将軍の命のままにせん』と。
是日、(二十九)風霾晝昏し。
哺後、徳戡、御厩の馬を盗み、潜に兵刃を厲ぐ。
是夕、元禮・裵虔通、閣下に直し、専ら殿内を主る。
唐奉義、城門を閉づるを主る。
虔通と相知り、諸門、皆、鍵を下さず。
三更に至り、徳戡、東城に於て兵を集め、數萬人を得、火を挙げて城外と相應ず。
帝、火を望見し、且つ外の諠囂するを聞き、『何事ぞ』と問ふ。
虔通對へて曰はく、『草坊、火を失し、外人共に之を救ふのみ』と。
時に内外隔絶し、帝、以て然りと為す。
智及、孟秉と與に、(三〇)城外に於て千餘人を集め、(三一)候衛虎賁馮普樂を劫して、兵を布き衢巷を分守せしむ。
(三十二)燕王倓、變有るを覺り、夜、芳林門の側の水竇を穿ちて入り、玄武門に至り、詭り奏して曰はく、『臣猝に風に中り、命、俄頃に懸る。請ふ面辭するを得ん』と。
裵虔通等、以て聞せず、之を執囚す。
丙辰、天未だ明けず。
徳戡、虔通に兵を授け、以て諸門の衛士に代わらしむ。
虔通、門より、數百騎を將いて成象殿に至る。
宿衛の者『賊有り』と傳呼す。虔通乃ち還りて諸門を閉ぢ、獨り東門を開き、殿内の宿衛の者を驅り、出でしむ。
【二六】事、前巻前年に見ゆ。
【二七】隋初、門下省は城門・尚食・尚薬・符璽・御府・殿内等の六局を統べ、各々直長あり。煬帝、城門・尚食・尚薬・御府等の五局を以て殿内省に隷し、符璽監を改めて郎と為す。城門に校尉を置く。後又校尉を改めて城門郎と為す。又、司醫・醫佐等の官を置く、醫正は即ち司醫なるべし。勲侍は三侍の一なり。
【二八】帝、左右領左右府を改めて左右備身府と為す。
【二九】霾。土を雨らすなり。
【三〇】城外。江都宮城の外を請ふ。
【三一】左右候衛は晝夜巡察するを主る、故に之を劫す。普楽は蓋し虎賁郎将なり。
【三二】倓は元徳太子昭の子、代王侑の弟。
『続国訳漢文大成』経子史部 第11巻,国民文庫刊行会,昭3至7. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1239984 (参照 2024-10-26)